あたしちゃん、行く先を言って ー太田省吾全テクストよりー
作品概要
2007年に亡くなった太田省吾は、京都造形芸術大学映像・舞台学科の創設にも関わり、京都の演劇とも深い関わりを持つ。三浦の初期の作品『Jericho』や『三人姉妹』を激賞し、京都移転後の地点を見守ってくれた人でもあった。2007年に刊行された大部の「太田省吾劇テクスト集(全)」をはじめ未収録の批評やエッセイも含めた全てのテキストを自由にコラージュして、ひとつの舞台にできないかという一年がかりのプロジェクトであった。




撮影:冨田了平(行程2)/清水俊洋(京都公演)/青木司(東京公演)
2009
日程・会場
2009.5.13-15【行程1】京都芸術センター フリースペース
2009.7.3-5【行程2】川崎市アートセンター アルテリオ小劇場
2009.9.8-13 京都芸術劇場 studio21
2010
日程・会場
2010.1.22-31 吉祥寺シアター
テクスト
太田省吾
構成・演出
三浦基
出演
安部聡子
石田大
大庭祐介
窪田史恵
小林洋平
谷弘恵
スタッフ
演出助手:村川拓也
照明:吉本有輝子
映像:山田晋平
美術:杉山至+鴉屋
音響:堂岡俊弘
衣裳:堂本教子
舞台監督:鈴木康郎+鴉屋
照明オペレーター:伊藤泰行
映像オペレーター:田中章義
宣伝美術:納谷衣美
広報:野口まどか
制作:田嶋結菜
京都芸術センター制作支援事業
主催
地点 川崎市アートセンター[川崎公演] 財団法人武蔵野文化事業団[東京公演]
共催
京都芸術センター[京都公演]
共催・共同製作
京都造形芸術大学舞台芸術研究センター
協力
Kyoto DU 有限会社青戸建材店 有限会社オサフネ製作所
助成
平成21年度文化芸術振興費補助金(芸術創造活動特別推進事業)
財団法人セゾン文化財団 EU・ジャパンフェスト日本委員会 アサヒビール芸術文化財団
劇評
演劇史の記憶はどのように継承されるのか
太田省吾が逝去して今年で3年目になる。『小町風伝』、『水の駅』のような沈黙劇の傑作によって、近代以降の日本の舞台芸術史を代表する作家であった彼のことを、人々はいまどれだけまともに記憶しているだろうか? 生前の彼の舞台作品やたたずまいに接した人々には忘れがたい痕跡をとどめているとしても、こと太田省吾に関する限り、それだけでは十分ではない。なぜなら太田の究極的な目的は、乱暴な言い方をすれば、傑作を残すことにあったわけではなく、「いまここに生きている私(たち)」の場所から「演劇」の自明性を疑い、「演劇」に対してたえず生きた問いを投げかけつづけることにあったからである。だから、問題は未来にあるのだ。かつて太田自身が書いた言葉を引用すれば、「劇には分厚い力がある」(『劇の希望』)。21世紀において、ますます「演劇」の制度的限界が露呈しはじめていても、いまなおそれは曖昧な微笑をうかべて人を誘惑しつづける(「演劇」には本来的にポピュリストの才能がある)。それゆえに、太田省吾を記憶する、ということは、とりもなおさず、彼が全身全霊をかけて提出した「問い」を受けとめ、生きた応答を投げかえすという現在形の行為でしかありえないのだ。
劇団地点の新作公演における演出家・三浦基の問題意識も、まさにその点にあったといってよい。彼は、特定の戯曲の再演ではなく、すべての戯曲と演劇論、エッセイ、すなわち太田が書き残した「全テクスト」を、上演のためのテクストとして召喚することを選択した。注意深くみれば、三浦がこうした方法をあえて選択した理由が、まさにそうすることを通じて、彼なりの太田省吾という問いそのものに対する応答を、生きた応答として提出することにあったことが見えてくる。「行程1」(5月、京都)「行程2」(7月、川崎)という二度のワークインプログレスを経て行われた今回の上演では、そのことが、これまで以上に明確な姿をとって立ち現れていた。タテ7m、ヨコ30m、高さ5.5mという奥行きの極端に浅い演技空間は、どの席の観客にとっても目近な光景でありつつも、全体を一度に見渡すことが不可能なつくりになっている。夥しい数のコンクリート・ブロックが、どこか川を思わせる形状に配置されている空間全体は、太田作品に頻出する生者と死者の境界を暗示する。おそらくいま最も油が乗っている地点の俳優陣のなかでも、太田の問いが何であったのかを鮮烈に印象付けたのは、やはり安部聡子の「声」であろう。「声を出すことを」をめぐる初期論評集から引用された太田のテクストを、およそ劇場で耳にしたことのない巨大な陰影(伝わることの限界は承知している)をはらんだ安部の「声」が、まさに沈黙劇の起源に関わる発語の問いを発語するとき(背後には『水の駅』の劇中音楽だったオーボエ協奏曲が大音量で流れている)、沈黙と発語をめぐる根源的な葛藤のありようが、見事に変奏されていたといえるだろう。だが、ある意味ではそれ以上に印象的だったのは冒頭場面である。開演のアナウンスが終わると、しばらくして6人の俳優たちが、気負いない足取りで下手から入場し、バラバラ立ち位置につく。最初は錯覚かと疑うのだが、よく目を凝らしていると、それぞれの俳優が非常にゆっくりとした速度で、確かに揺らいでいるのが認識される。その揺れる身体にはほんのわずかな質量しか感じられず、まるで木の葉が風に揺れているような揺らぎなのである。そこには沈黙劇の曖昧な模倣など一切なく、にもかかわらず、沈黙劇が何であったのかを考え抜いた末に、演出家が到達した身体論の厚みがあった。俳優の身体が、ただの存在ではなく思考の軌跡に他ならないことを、具体的感触として示していた舞台は、近年稀である。同時にまた、こうした三浦の試みが、現代日本の舞台芸術にあって、きわめて孤立したものであることも銘記しておかなければならない。徹底的にテクストを読み込むこと、そこにある問いの形を見極め、現在時における上演というもう一つの形へと翻訳すること。「演出家」という職業にとって必然的な作業の徹底化がかえって孤立を導くことは、いつの時代でも同じかもしれない。だが、この作品は、こうした長い作業プロセス自体が、結局のところ現代における過ぎた贅沢品にすぎないのかどうか、という今日的な問いも、それ自体として提起している。あとは観客の番であろう。私自身は、いまだからこそあえてその贅沢を擁護すると言いたい。(この作品の京都公演は、劇団地点と京都造形芸術大学舞台芸術研究センターの共催という形式で行われた。同センターの主任研究員である私は、この作品に対して完全な客観性を主張できる立場にはない。だが、この拙文が普通の劇評ではありえないとしても、自分の目撃したものには忠実であるべきであると考え筆をとった。その経緯はここに記しておきたい。)
七ツ寺通信
森山直人
劇評
極限の沈黙劇考える演劇
劇団地点の新作は、「水の駅」などの沈黙劇で知られる劇作家・演出家、太田省吾へのオマージュ。構成・演出の三浦基は、その戯曲や評論文を引用して「演劇について考えるための演劇」を試みた。
6人の俳優は、回廊状に延びた細長い空間の、上手から下手までを移動し、太田の戯曲に記されながら実際には発語されなかったせりふをしゃべる。彼らは何者なのか、名前やキャラクター設定はもちろん、死者なのか生者なのかさえあいまいなままだ。
通常、プロセニアム(額縁状)の劇場では、額縁の内側(舞台上)と外(客席)は明確に区切られ、客席からは、上手から下手まで一つのアングルで見渡すことができる。観客は、舞台上で起きるすべてを「劇」として受容し、感動やカタルシス(浄化作用)は舞台から客席へと放散される。 しかし、異様に横長にしつらえた本作の客席からは、舞台上の一部分が必ず視野からはみ出してしまう。その結果、観客は首を左右に動かし、能動的に「見るもの」と「見ないもの」を選択せざるをえない。
大声で叫ぶ人物、舞台上に並んだコンクリート・ブロックを動かす人物、2か所に設置された液晶画面の映像……。劇的なもの、あるいは物語や事件の「予感」が観客の視線を引きつける。だが、終演に至るまで、ついにそれらを見いだすことはできない。
板の上で起きる事象は「虚構」で「物語」だという観客側の固定観念を三浦はこの作品で疑い、突き崩そうと試みる。つまり、起承転結のある物語だけが劇ではなく、評論や詩も舞台空間で表現可能なのだと。
近代劇の最も重要な要素であった言葉を極限まで削り、身体表現の一つ一つを細かく分析した太田は「劇とは何か」を探究し続けた演劇人だった。その仕事を検証し、引き継ぐ前衛作品が、晩年の太田が数々の実験舞台を制作した同じ劇場で生まれたことは感慨深い。
読売新聞 2009.10.1
坂成美保
劇評
批評性の高い鎮魂の劇
演劇を演劇たらしめることを求めて沈黙や超スローな動作など、削りに削った表現で、世界的な前衛劇を創造した劇作・演出家の太田省吾が亡くなって3年になろうとしている。私淑した三浦基が、京都の劇団「地点」を率いて構成・演出した「あたしちゃん、行く先を言って」は、批評性の高い鎮魂の劇だ。
全11シーンは、太田の遺した戯曲や評論の章句に、歌や天気予報の声などを加えたコラージュ風の構成。前衛作の断片の組み合わせだから、とっつき難い。しかし、分かりやすい娯楽劇が氾濫する今、こんな舞台があっても良い。
演劇の必須要素は、上演する現在の一瞬にしか存在しない俳優の体と言葉。三浦はこの太田命題に果敢に取り組む。引用作は「裸足のフーガ」など10編以上の戯曲と、「飛翔と懸垂」「裸形の劇場」など五つの演劇論集。横長の黒い裸舞台に、コンクリートブロックの小道と、階段を設ける。液晶画面は展開と無関係な風景を映す。俳優の登退場の区別も曖昧だ。
一貫した物語も、リアルな演技、台詞術もない。主語と述語の関係も混乱させる。俳優は歩き、走り、台詞の間や抑揚を変えて爽快に異化する。 太田の近代劇を批判する言説が語られるシーンで、台詞の繰り返しを使った異化が効く。太田の所説すら意味はずらされ、言葉のリズムとなる。歌を背景にした詩の不規則な朗読シーンや次第に高まる死のイメージは、ブロックがたてる衝突音と共鳴し、硬質の美がある。反通俗を楽しむか、難しいと退屈するか。反応は分かれる。
出演は安部聡子、石田大、大庭裕介、窪田史恵、小林洋平、谷弘恵。皆若く、元気な体と声を持つ。匿名性のある透明さが清潔だ。
朝日新聞 2010.1.29
山本健一
/blog/blog_comments/captcha
| 作品概要 | 2007年に亡くなった太田省吾は、京都造形芸術大学映像・舞台学科の創設にも関わり、京都の演劇とも深い関わりを持つ。三浦の初期の作品『Jericho』や『三人姉妹』を激賞し、京都移転後の地点を見守ってくれた人でもあった。2007年に刊行された大部の「太田省吾劇テクスト集(全)」をはじめ未収録の批評やエッセイも含めた全てのテキストを自由にコラージュして、ひとつの舞台にできないかという一年がかりのプロジェクトであった。 |




撮影:冨田了平(行程2)/清水俊洋(京都公演)/青木司(東京公演)
| 2009 | |
|---|---|
| 日程・会場 |
2009.5.13-15【行程1】京都芸術センター フリースペース
2009.7.3-5【行程2】川崎市アートセンター アルテリオ小劇場 2009.9.8-13 京都芸術劇場 studio21 |
| 2010 | |
| 日程・会場 |
2010.1.22-31 吉祥寺シアター
|
| テクスト | 太田省吾 |
| 構成・演出 | 三浦基 |
| 出演 |
安部聡子 石田大 大庭祐介 窪田史恵 小林洋平 谷弘恵 |
| スタッフ |
演出助手:村川拓也 照明:吉本有輝子 映像:山田晋平 美術:杉山至+鴉屋 音響:堂岡俊弘 衣裳:堂本教子 舞台監督:鈴木康郎+鴉屋 照明オペレーター:伊藤泰行 映像オペレーター:田中章義 宣伝美術:納谷衣美 広報:野口まどか 制作:田嶋結菜 |
| 京都芸術センター制作支援事業 | |
| 主催 | 地点 川崎市アートセンター[川崎公演] 財団法人武蔵野文化事業団[東京公演] |
| 共催 | 京都芸術センター[京都公演] |
| 共催・共同製作 | 京都造形芸術大学舞台芸術研究センター |
| 協力 | Kyoto DU 有限会社青戸建材店 有限会社オサフネ製作所 |
| 助成 |
平成21年度文化芸術振興費補助金(芸術創造活動特別推進事業) 財団法人セゾン文化財団 EU・ジャパンフェスト日本委員会 アサヒビール芸術文化財団 |
| 劇評 |
演劇史の記憶はどのように継承されるのか 太田省吾が逝去して今年で3年目になる。『小町風伝』、『水の駅』のような沈黙劇の傑作によって、近代以降の日本の舞台芸術史を代表する作家であった彼のことを、人々はいまどれだけまともに記憶しているだろうか? 生前の彼の舞台作品やたたずまいに接した人々には忘れがたい痕跡をとどめているとしても、こと太田省吾に関する限り、それだけでは十分ではない。なぜなら太田の究極的な目的は、乱暴な言い方をすれば、傑作を残すことにあったわけではなく、「いまここに生きている私(たち)」の場所から「演劇」の自明性を疑い、「演劇」に対してたえず生きた問いを投げかけつづけることにあったからである。だから、問題は未来にあるのだ。かつて太田自身が書いた言葉を引用すれば、「劇には分厚い力がある」(『劇の希望』)。21世紀において、ますます「演劇」の制度的限界が露呈しはじめていても、いまなおそれは曖昧な微笑をうかべて人を誘惑しつづける(「演劇」には本来的にポピュリストの才能がある)。それゆえに、太田省吾を記憶する、ということは、とりもなおさず、彼が全身全霊をかけて提出した「問い」を受けとめ、生きた応答を投げかえすという現在形の行為でしかありえないのだ。 劇団地点の新作公演における演出家・三浦基の問題意識も、まさにその点にあったといってよい。彼は、特定の戯曲の再演ではなく、すべての戯曲と演劇論、エッセイ、すなわち太田が書き残した「全テクスト」を、上演のためのテクストとして召喚することを選択した。注意深くみれば、三浦がこうした方法をあえて選択した理由が、まさにそうすることを通じて、彼なりの太田省吾という問いそのものに対する応答を、生きた応答として提出することにあったことが見えてくる。「行程1」(5月、京都)「行程2」(7月、川崎)という二度のワークインプログレスを経て行われた今回の上演では、そのことが、これまで以上に明確な姿をとって立ち現れていた。タテ7m、ヨコ30m、高さ5.5mという奥行きの極端に浅い演技空間は、どの席の観客にとっても目近な光景でありつつも、全体を一度に見渡すことが不可能なつくりになっている。夥しい数のコンクリート・ブロックが、どこか川を思わせる形状に配置されている空間全体は、太田作品に頻出する生者と死者の境界を暗示する。おそらくいま最も油が乗っている地点の俳優陣のなかでも、太田の問いが何であったのかを鮮烈に印象付けたのは、やはり安部聡子の「声」であろう。「声を出すことを」をめぐる初期論評集から引用された太田のテクストを、およそ劇場で耳にしたことのない巨大な陰影(伝わることの限界は承知している)をはらんだ安部の「声」が、まさに沈黙劇の起源に関わる発語の問いを発語するとき(背後には『水の駅』の劇中音楽だったオーボエ協奏曲が大音量で流れている)、沈黙と発語をめぐる根源的な葛藤のありようが、見事に変奏されていたといえるだろう。だが、ある意味ではそれ以上に印象的だったのは冒頭場面である。開演のアナウンスが終わると、しばらくして6人の俳優たちが、気負いない足取りで下手から入場し、バラバラ立ち位置につく。最初は錯覚かと疑うのだが、よく目を凝らしていると、それぞれの俳優が非常にゆっくりとした速度で、確かに揺らいでいるのが認識される。その揺れる身体にはほんのわずかな質量しか感じられず、まるで木の葉が風に揺れているような揺らぎなのである。そこには沈黙劇の曖昧な模倣など一切なく、にもかかわらず、沈黙劇が何であったのかを考え抜いた末に、演出家が到達した身体論の厚みがあった。俳優の身体が、ただの存在ではなく思考の軌跡に他ならないことを、具体的感触として示していた舞台は、近年稀である。同時にまた、こうした三浦の試みが、現代日本の舞台芸術にあって、きわめて孤立したものであることも銘記しておかなければならない。徹底的にテクストを読み込むこと、そこにある問いの形を見極め、現在時における上演というもう一つの形へと翻訳すること。「演出家」という職業にとって必然的な作業の徹底化がかえって孤立を導くことは、いつの時代でも同じかもしれない。だが、この作品は、こうした長い作業プロセス自体が、結局のところ現代における過ぎた贅沢品にすぎないのかどうか、という今日的な問いも、それ自体として提起している。あとは観客の番であろう。私自身は、いまだからこそあえてその贅沢を擁護すると言いたい。(この作品の京都公演は、劇団地点と京都造形芸術大学舞台芸術研究センターの共催という形式で行われた。同センターの主任研究員である私は、この作品に対して完全な客観性を主張できる立場にはない。だが、この拙文が普通の劇評ではありえないとしても、自分の目撃したものには忠実であるべきであると考え筆をとった。その経緯はここに記しておきたい。) 七ツ寺通信 森山直人 |
| 劇評 |
極限の沈黙劇考える演劇 劇団地点の新作は、「水の駅」などの沈黙劇で知られる劇作家・演出家、太田省吾へのオマージュ。構成・演出の三浦基は、その戯曲や評論文を引用して「演劇について考えるための演劇」を試みた。 6人の俳優は、回廊状に延びた細長い空間の、上手から下手までを移動し、太田の戯曲に記されながら実際には発語されなかったせりふをしゃべる。彼らは何者なのか、名前やキャラクター設定はもちろん、死者なのか生者なのかさえあいまいなままだ。 通常、プロセニアム(額縁状)の劇場では、額縁の内側(舞台上)と外(客席)は明確に区切られ、客席からは、上手から下手まで一つのアングルで見渡すことができる。観客は、舞台上で起きるすべてを「劇」として受容し、感動やカタルシス(浄化作用)は舞台から客席へと放散される。 しかし、異様に横長にしつらえた本作の客席からは、舞台上の一部分が必ず視野からはみ出してしまう。その結果、観客は首を左右に動かし、能動的に「見るもの」と「見ないもの」を選択せざるをえない。 大声で叫ぶ人物、舞台上に並んだコンクリート・ブロックを動かす人物、2か所に設置された液晶画面の映像……。劇的なもの、あるいは物語や事件の「予感」が観客の視線を引きつける。だが、終演に至るまで、ついにそれらを見いだすことはできない。 板の上で起きる事象は「虚構」で「物語」だという観客側の固定観念を三浦はこの作品で疑い、突き崩そうと試みる。つまり、起承転結のある物語だけが劇ではなく、評論や詩も舞台空間で表現可能なのだと。 近代劇の最も重要な要素であった言葉を極限まで削り、身体表現の一つ一つを細かく分析した太田は「劇とは何か」を探究し続けた演劇人だった。その仕事を検証し、引き継ぐ前衛作品が、晩年の太田が数々の実験舞台を制作した同じ劇場で生まれたことは感慨深い。 読売新聞 2009.10.1 坂成美保 |
| 劇評 |
批評性の高い鎮魂の劇 演劇を演劇たらしめることを求めて沈黙や超スローな動作など、削りに削った表現で、世界的な前衛劇を創造した劇作・演出家の太田省吾が亡くなって3年になろうとしている。私淑した三浦基が、京都の劇団「地点」を率いて構成・演出した「あたしちゃん、行く先を言って」は、批評性の高い鎮魂の劇だ。 全11シーンは、太田の遺した戯曲や評論の章句に、歌や天気予報の声などを加えたコラージュ風の構成。前衛作の断片の組み合わせだから、とっつき難い。しかし、分かりやすい娯楽劇が氾濫する今、こんな舞台があっても良い。 演劇の必須要素は、上演する現在の一瞬にしか存在しない俳優の体と言葉。三浦はこの太田命題に果敢に取り組む。引用作は「裸足のフーガ」など10編以上の戯曲と、「飛翔と懸垂」「裸形の劇場」など五つの演劇論集。横長の黒い裸舞台に、コンクリートブロックの小道と、階段を設ける。液晶画面は展開と無関係な風景を映す。俳優の登退場の区別も曖昧だ。 一貫した物語も、リアルな演技、台詞術もない。主語と述語の関係も混乱させる。俳優は歩き、走り、台詞の間や抑揚を変えて爽快に異化する。 太田の近代劇を批判する言説が語られるシーンで、台詞の繰り返しを使った異化が効く。太田の所説すら意味はずらされ、言葉のリズムとなる。歌を背景にした詩の不規則な朗読シーンや次第に高まる死のイメージは、ブロックがたてる衝突音と共鳴し、硬質の美がある。反通俗を楽しむか、難しいと退屈するか。反応は分かれる。 出演は安部聡子、石田大、大庭裕介、窪田史恵、小林洋平、谷弘恵。皆若く、元気な体と声を持つ。匿名性のある透明さが清潔だ。 朝日新聞 2010.1.29 山本健一 |
/blog/blog_comments/captcha





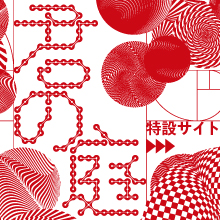



「ね、なにか言って。」
「話してるじゃないか。」
「〈愛しているよ〉とかって。ね、普通のこと言って。〈可愛くってたべちゃいたい〉とかって。」
「愛してるよ。可愛くってたべちゃいたい。」
これは太田省吾の台詞であるが、あえてタブーを犯すための苦労がにじみ出ている。さらに氏は<沈黙>のうちにこの台詞を用い、つまり発語しなかったわけだが、そのようにして演劇のタブーを描ききったのである。今、大事なことは、しかし、私は発語したいと思っているということ。この扱いにくい作家を白昼堂々ひきずり出そうとしているわけで、これはタブーにタブーが重なった、複雑な今日の演劇であり、私なりの賭けなのです。
三浦 基
出典:当日パンフレット