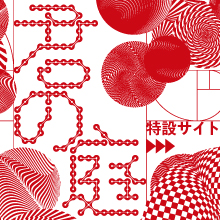マヤコフスキー研究会 第3回(後半)
講師:杉山博昭(早稲田大学高等研究所助教)、鴻英良(演劇批評家)
聖史劇からアヴァンギャルド演劇まで~マヤコフスキーの視界を覗く
鴻:初めまして、鴻英良と申します。演劇批評家を詐称して活動しています。なぜ私がここにいるのかということなんですけども。30~40年ほど前まで、ロシア文学をやっていまして、ロシアの象徴派の詩人のアレクサンドル・ブロークという人について研究していました。1906年にアレクサンドル・ブロークという詩人が戯曲を書くんですね『バラガンチク』という、直訳すると「見世物小屋もどき」というんですが、それを演出したのがメイエルホリドだったということで、その関係で演劇について調べるようになって、そしてなんとなくロシア・ソビエト演劇についての研究を始めたんですけれども、いろいろ事情があって辞める羽目になってですね、ですから今はロシア文学者を名乗ることをやめています。1979年のユリイカ10月号に「ロシアの民衆的ユーモア~ミステリヤ・ブッフ論のために」というタイトルで、そんなに長くない、4ページほどの文章を書きました。まあ、そういったことも含めて、30年ぶりにマヤコフスキー、メイエルホリド関連の本を読み直しているところです。
いまの杉山さんの話を聞きながらですね、しかしながら私はマヤコフスキーとかメイエルホリドとかを思い出すのではなく、やはり同じ時代の非常に重要なソビエト・ロシアの演出家であるニコライ・エヴレイノフのことをむしろ思い出していたんです。エヴレイノフに関しては、日本語で一つ、『生の演劇』だったか、翻訳が出ているので読むことができる、ということと、日本語で出ているロシア・アヴァンギャルド、演劇関係の書物を紐解くと、いくつか彼が何をやってきたのかを調べることができるので、この『ミステリヤ・ブッフ』をやるにあたってですね、エヴレイノフを読むといいんじゃないかと思います。それで、なぜエヴレイノフを思い出したのかというと、今の杉山さんの話を聞きながら、彼の演劇観というものにむしろ非常に近いと思ったからなんです。
僕はこの十年ほどは、古代ギリシャの演劇、悲劇とコメディアについて調べていて、いまその本を執筆準備中なんですけれども、いわゆる西洋の演劇史を辿っていくときに、演劇の起源として一般的にギリシャ悲劇を想定するというのが、どちらかというと王道なんですね。ところが、エヴレイノフは演劇の起源はギリシャ悲劇ではないと言ったわけです。
最初の話のほうで、「王の入城儀礼」の話が出てきました。つまり聖史劇の起源としての、あるいは特徴としての、エレメントとしての王の入城儀礼という話をしていただきましたが、エヴレイノフは古代バビロニアにおける王の入城儀礼、具体的には「マードックの入城儀礼」というのが演劇の起源であると言ったわけです。その入城儀礼というのは当然のことながら、王がその当時の都市の城壁の外側から、行進・行列をしながらやってきて、そして城の中に入っていく。それを要するに華々しく華麗にやると。当然のことながら、山車のようなものに乗って、そしてそこで華麗な演技をしながら「私は王である」というようなことをやると。さらに行列の周りには、道化師たちがいて、その道化師たちが滑稽な身振りで人を笑わせたりというような形でやる、そこから演劇が生まれてきたのだ。つまり、華麗で有機的な行列、先ほども何度も出てきましたがその行列がいろいろな場所で立ち止まり、一つの見世物的なものを演じる。そしてまた行列を続けていき、またどこかで立ち止まる。という風に練り歩いた後に城の中に入っていく。このときに成されたさまざまな事柄が、儀礼から独立・自立するようになって演劇が生まれたのであって、その後にギリシャ悲劇がやってきたのであるということを書いているんです。
彼のいくつかの有名な著作の中にこれは翻訳はないんですけれども、『ロシア演劇史』というものがあって、ロシアにおいても同じように農耕儀礼というようなことがあり、それについても説明をしつつ、ギリシャ悲劇以前の、ギリシャにおける神話的世界での儀礼についての本を書いているんですね。そういう意味でエヴレイノフはまさに今日お話をしてくださった内容に即すような形で演劇を展開していったわけです。その中で一つ有名なものに1920年の革命3周年記念のときに行われた壮大な野外群集劇で『冬宮奪取』と訳されています。ロシア革命のときに、「冬宮」、現在のエルミタージュ美術館になっているところですけれども、ペテルブルクのネヴァ川沿いにある、それを革命に参集した人たちが奪取するわけですよね。そしてロシアが、帝政が、崩壊するのですが、その歴史的な出来事を再現する巨大ページェント、市街群集劇として、かつそれは最終的にエルミタージュにたどり着くわけですけれども、ペトログラードのさまざまな地域で、それぞれの労働者たちが集結してですね、さまざまな地域から冬宮へ行進をするんですね。さっきとほとんど同じような話です(笑)、冬宮に結集していくわけです、行列しながら。そして最後に冬宮広場というところに入って、赤衛軍と白衛軍との戦いを舞台上で演じる。戦いが終わった後に冬宮のなかに赤衛軍が入って行ってですね、それ以降は影絵劇になって窓に戦闘が継続されている。そのような形で革命3周年を祝福するというですね、形態としても聖史劇と似ているのと、宗教を礼賛するという形で行われていた聖史劇が、革命を礼賛するという別の形で展開されていった。ロシア革命後、数年間の中で行われた演劇の中でいくつか重要な作品を個別に挙げるとすると、これがおそらくそのうちの一つなんですね。そういうようなページェント的、儀礼的、革命的というのがその前後にたくさん行われていて、それについてはかなり詳しい本があって、写真がいろいろ残っていて、どんな雰囲気でやられたんだというのはかなり詳しく見ることができます。たぶん楯岡さんが全部持っていると思うので、貸してもらって読むのがいいと思います。
この『ミステリヤ・ブッフ』ですけれども、最初に上演されたのが1918年11月7日つまり革命一周年記念のときに、マヤコフスキーが夏ごろに書き始めて、9月かな、書き終えたんですよね。そして1921年にメイエルホリドの演出によって再び上演されると。メイエルホリドが1921年の革命4周年のときに上演するにあたって、マヤコフスキーがテキストを少し書き直しているんですね。送っていただいた翻訳は1918年に上演されたときのテキストから小笠原豊樹さんが訳したものですね。小笠原豊樹は有名な詩人・岩田宏の本名ですね。私は学生時代のときに岩田宏が本名で、小笠原豊樹がペンネームだと思っていたんですけど。小笠原豊樹のほうがかっこいいじゃないですか。それを敢えて要するに平凡な名前をペンネームにして詩を書いていたんですね。つい最近まで生きていたということを私は知らなかったんですけれども、昨年亡くなったんですね。
小笠原さんとは1度だけ会ったことがあるんですけれども。わたしが利賀村に鈴木忠志の芝居を見に行って、そして利賀フェスティバル以前の「利賀村での宴の夜3」というものに私は行ったんですけれども、78年ですかね、その直後に江川卓と岩田宏と会って、まあ彼らが会っているところに私がいただけなんですけれども。利賀村に行った話をしたら、「お前みたいなやつには演劇をやる資格がない」と小笠原さんに言われたんですよ。なぜですかと聞いたら、「演劇は都市のものだよ」と非常にはっきりと断言しましたね。つまり都市から逃亡して田舎に逃げたやつの芝居を見に行くような人間に演劇を研究する資格はないと言われたんです。この辺ね、非常に教条主義的ですごい面白いなと思ったんです。
マヤコフスキーはずっとペテルブルグで、都市の中心で演劇をやっているんですよね。エヴレイノフは農村に非常に興味を持っていたんですよね。で、マヤコフスキーはね都市の演劇を作るにあたってエヴレイノフ的なページェントを非都市的、あるいは非中心的というような構造の中に解体しつつ『ミステリヤ・ブッフ』という作品を書いたんですね。この『ミステリヤ・ブッフ』の展開それ自体からもわかるように、これは舞台は都市ではないんですね。舞台はさまざまな場所なわけですね。地球の亀裂から、悪魔たちが門のようなところから出てくる。どこですか、という話になると、これは都市ではないわけです。大洪水だと、エスキモーが叫んでましたが、エスキモーの人たちが叫んでるわけで、北極ですね。大洪水が起こる、で、方舟を作らなくちゃと叫んでいる人たちが、いろいろなところから来ている人たちが集まっていると。そこがどこかというのは実はよく分からない。まあ少なくともペテルブルグではないだろうと。で、そいつらが方舟に乗って、そして約束の地を探しながら点々とするという、この構図はそもそも元があるんだって言うんですよ。要するに現代の『オデュッセイア』なんだ、つまりこれは叙事的見世物であると。叙事詩的、つまり『オデュッセイア』から継続されて書かれた物語であるということですね。最初のページェント、ページェントというのは『オデュッセイア』の演劇的というか広場的、街頭的表現というようなことですね。『オデュッセイア』についてですが、トロイア戦争が終わった後、トロイアでギリシャ軍が勝利したときに、ギリシャの兵士たちは自分たちの国に帰って行くわけですけども、その途中に死んだ人たちも沢山いるわけですね。エジプトに流れ着いたメネラオスとか沢山いたわけです。最終的にオデュッセウスが自分の故郷に辿り着く話だと思っている人が多くて、帰還の話と考えている人が多いですが、アンドレ・ボナールという人に言わせるとそれは間違いだと。なぜギリシャの商人、船乗りたちがこの作品を好んで愛唱したのか。なぜならばそれは、乗り出して行く話だからだ。ギリシャの商人たちがですね、オデュッセウスが見知らぬ土地へと旅立って、多くの交渉を経て、ある種略奪をしてですね、そして新しい体験をしつつ略奪品を持って帰ってきていた。つまり出て行く話なんですね。『ミステリヤ・ブッフ』も帰還の物語ではなく、洪水という、この大洪水は革命のことなんだとよく書かれていますが、革命にあおられて外に旅立っていき、新しいものを構築していく物語だと。そのときに多くの抵抗を受けると。その抵抗する者たちの中に、労働者に対する抵抗を試みているのが、ブルジョワジーとか王侯貴族とかきれいな人々、⟨清潔な人々⟩といわれている人ですよね。もう一つが悪魔たち、そして天使たちも基本的に克服しなければならない対象なんですね。そのような無限の闘いの果てに、自分たちはオブジェたちの世界を作り上げようとするわけです。つまり、物・事物。この当時のソビエト文化のキーワードは「事物のユートピア」といって、これを構築する労働者たち、つまりプロレタリアを要するに一つの聖史劇的ページェントとともに上演していくと。しかしながらこれは単なる聖史劇ではない。「ブッフ」であるというわけです。「ブッフ」というのは道化芝居ということですよね。聖史劇と道化芝居が同居しなければならないと。そういう風にマヤコフスキー自身も言っていますしね。ミステリヤとは革命における偉大なる・崇高な部分、ブッフとは革命における滑稽なる・道化的な部分、その二つが同居する形で革命というものの只中においてですね、革命を賛美しつつその革命をどのような方向に向けて行くのか。すでに勝利はほぼ収めたはずではある、しかしながらそのものの展開も含めて現在進行形の革命賛歌を唱い上げると。しかしこれはあくまでも滑稽なのであるというわけです。
メイエルホリドの最初の重要な上演演目の一つである『バラガンチク』、この「バラガン」というのは定期市の小屋でそこで道化芝居を演じるわけですね。実は見世物小屋の主要登場人物は二組いて、一組は神秘家たちでもう一組がピエロ。つまり『ミステリヤ・ブッフ』というのは原型がアレクサンドル・ブロークの『バラガンチク』、この作品は神秘家たちの集会から始まるんですが、その集会の中で天使のようなマリアのような崇高なものの到来を待ち望んでいる、その神秘家たちの足元にうずくまって悲しげな顔をしている道化師・ピエロがいるわけです。そして、道化師・ピエロは自分をアルレッキーノだと信じていて、そこにやってくるのは美しい人ではなくて、神秘的な霊感を到来させる人でもなくて、コロンビーナなんだというわけですよ。ここで、道化芝居と神秘劇が重なると。ある意味ロシア・ソビエトのアヴァンギャルド演劇の出発点に象徴主義演劇といわれるものがあって、その象徴主義演劇が道化芝居であると、その系図の中にマヤコフスキーがいると考えたほうがいいんですね。そういったマヤコフスキーの資質というか、たぶん意識していたに違いないと。ここだけは私が思っているのであって、どうなのか分からないんですが、たぶんその系統の中にいるんだと思うんですね。
内容的にはそういう風に大雑把に言うことができるんですが、もうひとつはロシア革命以後のソビエト演劇というものが徐々に構成主義的な要素を強めていく、この流れの中にマヤコフスキーの『ミステリヤ・ブッフ』があって、いわゆる劇場の中で「第四の壁」を取り払ってその向こう側で展開されている現実風景を観客が覗き込むというような、よく言われているような形ではなくて、それだけではなくて、四つの壁全部を取っ払えとマヤコフスキーは考えていたと思うんですね。客席と舞台との境界線を取っ払えと。だから前のほうの座席は外してですね、舞台セットを客席の中まで押し込むと。たぶんみなさん見ていると思うんですけど、その当時の舞台装置の絵が残っているんです。地球の半球といいますか、北極のあたりを上にして3分の1くらいがあって、そこに「地球」と書かれていて、その上でエスキモーが座って演技を始めると。そして他の人たち、洪水に見舞われた人たちが、材木を使って方舟を建造しているんですね。ここら辺、演劇はいわゆる見るための美的な芸術作品ではなくて、生産活動なのだと、いわゆるソビエトのコミュニズムの精神をもとにですね、プロレタリアートが世界を作るんだ、そういうような形で自分たちで方舟を作るんだと。で、どうやら実際に作っていたようですね。つまり、ちゃんと建造・建設現場だったわけです。しばらくすると方舟がある程度完成してきて、甲板ができたり、マストができたり、方舟なのにマストはおかしいんじゃないかと思うんですけど…。その方舟が完成して、いろいろなところをまわり、地獄にも行くわけですね。すると地球が回転して、亀裂の向こう側から沢山の悪魔たちがあがってくるわけですね。いってみれば地球の下に悪魔がいるということですね。そしてもうひとつ、これは大島さんがおっしゃっていたと思うんですが、ロープが一本張ってあって、ラザレンコという人らしいですけど、ぴょんぴょんと悪魔たちと激しい動きをする。
何を話したいかというと舞台は垂直的なんです。そして初演のときは、マヤコフスキーが梯子を降りながらプロローグをしゃべったって言うんですよね。だからこれ三浦さんが最初のプロローグをロープか梯子を降りてきて途中で叫んだらいいんじゃないかと勝手なことを言いますが気にしないでください。この構成主義舞台という、建設・生産・垂直線、この演劇理念のもとになったのは何かというと、1914年に先ほどいった『バラガンチク』をオフィツェールスカヤ通りにあるスタジオでメイエルホリドが演出したときに、みんなをあっといわせた演出方法ですね。それは、単純なんですけど、舞台の上に台をつくって、そこにポンと乗ったんですね。それまで演劇というものは床でやるものだとずっと思われていたんですよ。構築体を作って乗ったというのは、目が覚めるようなものだったんですね。このときの理念が、『ミステリヤ・ブッフ』のメイエルホリド演出の中に完全に生かされたと。だからこうパンっと上るんですね、ピエロが飛び乗るんですよ。この垂直性。世界は垂直的でもあると。構築体はわれわれが建設するのだと、そういうような意味合い。その当時メイエルホリドが暖めていたその理念から、構成主義という具体的な展開の中で、現実化していく。そのためのテキストをマヤコフスキーがその後メイエルホリドに提供するようになっていくんですね。そういうような意味で、この『ミステリヤ・ブッフ』をマヤコフスキーが書いたということは、非常に大きな意味を持つんですね。「ミステリヤ」、「ブッフ」、「バラガンチク」、神秘主義者たち、道化、こういうような非常に画期的な流れだったんですね。
僕は知らなかったんですけど、小笠原さんが『マヤコフスキー事件』という本を書いていたんですね。1930年にマヤコフスキーは自殺したんじゃなくて、殺されたんじゃないかと。僕もだいたい思っていて、そう思っているロシア文学関係者は結構いるんですね。その本を読んでいないので分からないんですが、想像するに殺されたんじゃないかと。証拠はってなると難しいですが。メイエルホリドは国家反逆罪で処刑されていますね、1940年に。メイエルホリドは徐々に追い込まれて行って、具体的に告発されるのは1937年の12月ですけど、その後、どんどん追い込まれて39年に逮捕されて40年の2月に殺されているんですね。これほどあからさまに、告発されて処刑されているのとはちょっと違うんでね。マヤコフスキーの件は興味深いですね。愛人関係によるものというのが一般的な定説とされているんですけど、そういうことも含めて検証しなおしたほうがいいかなと思いますけど。もう一人、自殺したとされているけど、私は殺されたんじゃないかと思っているのは、ヴァルター・ベンヤミンですよね。彼はフランスから逃れて、スペイン国境を越えてポルト・ボウというところに着いたときに、フランスの出国ビザはもっていたけれども、スペインの通過ビザをもっていないと、直ちに帰れといわれて世を儚んで自殺したといわれています。でも本当は殺されたんじゃないかと思っている人がいます。私もそうです。殺害指令を出したのはね、アレクサンドル・コジェーヴですよ、かの有名な。でもこういうのって証拠がなかなか出てこないんですよね。つまり、スラヴォイ・ジジェクがコジェーヴはスパイの手先で、と何の証拠も挙げずに言うわけですよ。何でお前が知っているんだと思うんですが、それはジジェクがスパイだからですよ。だから私はスパイなんだから知っているんだよと、ジジェクは言っているわけです。そのような事実関係を調べなおしながら作品を見直すと、またいよいよ面白いことが出てくるんじゃないかなということで喋っています。
もう一つ大きな問題は、1989年、ベルリンの壁崩壊跡のソビエト連邦及び社会主義圏の崩壊ですよね。1917年の革命によって実現した社会主義国家というものが壊滅していった今、社会主義の理念とコミュニズムへの希求ということによって満たされてきたそうした作品群をどのような形で現代社会に位置づけるのかと。これは非常に難しい問題でこの問題をほとんどの人が避けていますよ。これはね、要するにほとんど日本の、日本だけじゃないけど、文化人・知識人の怠慢もいいところでね。いまじゃグローバル金融資本主義の虜になっているロシアと、名前を変えてほしいと思いますけど、中国共産党ですよね。そういうようなことも含めて、思想史的な考察が必要なんですよね。マヤコフスキーの『ミステリヤ・ブッフ』を上演するということは、そういう問題を改めて問いかける契機になるだろうと僕は思うんです。そういういわば世界史的な広がりの中で、この作品を読み直し、且つ上演しなおすというような作業が必要とされているときに、三浦さんが果敢にもですね、こうした問題を喚起するような上演に向けて準備をしているということが非常に意味のあることではないかなと思います。マヤコフスキーの『ミステリヤ・ブッフ』というのは、ソビエト最初の戯曲、最初のソビエト戯曲という風に、フェブラリスキーも論文書いていますね。最初のソビエト戯曲の顛末についてという、久しぶりに読み直し始めたんで、もう少しちゃんといろいろ調べようかなと思っているところです。
もう一つだけ大胆なことをいいますと、私は最近あるところでピタゴラスについて話をしたんですけど、要するにギリシャ悲劇とホメーロスの叙事詩との間の、ギリシャ悲劇の直前というか、100年くらい前にピタゴラスがいるんですけど、ギリシャ悲劇のもとは素材はベンヤミンが言っているように伝説ですよね。その伝説はホメイロスによって記録されて今残っていると。その叙事詩をピタゴラスの思考によって変換すると悲劇が誕生すると、これは近いうちに論文書きますけど。で、トルストイとドストエフスキーをマルクス、エンゲルスの思想で変換するとイプセンが出てくると。そのイプセンを上演するために、実は演出家が必要であったと。演出家の誕生と、近代戯曲の出現というのは同一なんですよ。その後に象徴派とか未来派とかいろんなものが出現してくるんですけど、例えばスタニスラフスキーとメイエルホリドの違いよりも、スタニスラフスキーが出現した後とその前というのは切断面が大きいと考えるべきなんです。テキスト解釈というものに対する必要性が出てきたんで、それでメイエルホリドのような人はその必要性に基づいて、革命後という状況の中でテキストを読み込んでいくという作業をしていたんです。ソビエト崩壊後の状況の中でのテキスト解釈というものをどのようにしてやって行くべきなのかということは非常に重要なことだと、私は思っているわけです。そういったわけで、久しぶりにロシア語も読みました。1年ぶりですかね。ということで私の話はこれで。
三浦:ありがとうございました。まだ時間ありますし、質問などあればどうぞ。
→次頁へ