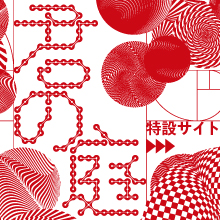杉山:ちょっとだけいいですか? あの、今のお話を聞いて先ほどいい忘れたことを思い出しまして、「ブッフ」、笑いに関してなんですけれども。そもそも聖史劇には笑いがたくさんありまして、それにさらに「ブッフ」かと。僕は最初思ったんですね。聖史劇の笑いだけじゃ足りないんだと。ただイタリアの聖史劇の笑いというのは大変に品がなくてですね、弱いものいじめをして、苦しんでいる弱いものを上から見て笑うというものが多くて、せむし男が怖がっているのを見て笑うとか、障害者へのいじめもありますし、病気で容姿が変わっているのを笑うとか、僕も話をしづらかったので今日も後に回していたら抜け落ちちゃったので、それをちょっと言い添えたいと思いました。また聖史劇自体が聖書のパロディじゃないですか、それをさらにパロディにするんだなと、それが面白いなと思ったんです。そのパロディがどんどん上書きされていき、いろいろな隙間ができるでしょうし、いろいろな力が動くでしょうし、面白いところだなと思いました。
鴻:涜神的な文化みたいなものというのはロシアにもあって、今日も盛んに出てきていたガブリエルとマリアですよね、あれについてロシア文学の父といわれるプーシキンが、『ガブリーリアータ』という『天使ガブリエルの物語』という長編詩を書いていて、マリアがなぜキリストを身ごもったのかということ、一般には処女懐胎といわれますが。天使が来るじゃないですか、天使に犯されるんですよ、その後にそばにいる聖霊がいるじゃないですか、鳩ですよ、鳩に犯されるんです。その後に父なる神がそれを見ていて、実は父なる神にも犯されたんだと。で、いったい誰の子どもかよくわからないと。得したのは誰かと、問いかけがなされていて。これが発禁になるんですね。ロシア正教会を愚弄するにも程があると。この話は実はアルメニアに伝承されている。そこに伝承されているものをプーシキンが使いながら、滑稽に聖書の物語を書き直したんじゃないかと。先ほども下品という話がでましたけど、ミステリヤにおける下品度。でもそれとはまたちょっと違いますよね。「ミステリヤ・ブッフ」という言葉を聞いたときに、僕はプーシキンのこの詩を最初から思い出していたんですけれども。先ほどのバフチンのカーニバル的な転倒というようなもの、笑いというものをどのように受け入れて行くのか、なおかつ転化していくのかということを『ミステリヤ・ブッフ』で考え直すというのは面白いなと思います。
それから、先ほどからアブラハムでしたっけ、スーズダリという古い教会の町があるんですね。モスクワから東へ数百キロいったところにある、キエフからモスクワに点々と移って行くときの、重要な宗教的聖地ができて行くわけですけど、そのアブラハムが、フィレンツェに行ったって言う話なんですか?
杉山:そうですね。
鴻:そしてそれでロシア人だから、書いたのはロシア語ですか?
杉山:そうですね。
鴻:イタリア語で訳が出ているんですか?
杉山:そうですね、いろいろな言語で出ていると思います。
鴻:ではロシア語でも読めるということですね。ということは1400年代にスーズダリの司教が、つまりロシア正教会の司教が、カトリックのフィレンツェの町を訪れて、いろんな聖史劇や宗教画を見て書いたと。
杉山:フィレンツェ公会議の出席者の一人だったといわれています。
鴻:何年ですか?
杉山:1438年~39年ですね。
鴻:今日話を聞いていてもう一つ思ったんですけど、1400年代の話が中心だったと思うんですね。そもそも聖史劇が1400年代。ちょうどダンテが『神曲』を書いてから100年後くらいということですね。ダンテの『神曲』といえば、やはり宗教的叙事詩ですよね。『オデュッセイア』もよく言われますけど。よく言われるのは『誰にロシアは住みよいか』というネクラーソフの叙事詩があって、「大酒呑み」というのが答えなんですけど、みんなで飲んだくれていると。わたしは学生のときそれを読んで、そうか私は正しかったのかと思いましたけど。要するに元を辿るといくつかのモデルがあって、ひとつはホメーロスでもうひとつはネクラーソフで、ダンテの『神曲』もどこかに書かれているのかもしれませんが今のところ見つけられていない。書けるか分からないんですけど、今私は「ダンテとベケット」という文章を準備しています。要するに、ベケットがダンテの影響をもろに受けているのは誰でも知っていることなんですけれども、ちそういうようなテーマもあるかなと私はなんとなく思っています。
三浦:楯岡さん何かありますか。
楯岡:本当に大変面白くうかがいました。ありがとうございました。
杉山さんのお話の中で伺いたいことがあります。
ひとつはテクニカルな問題で、音楽についてはあまりよく分かっていないという話があったんですが、台詞はどんな風に、歌うように朗唱されたのか、それとも諳誦されたのかということが一つと、先ほどバフチンの話も出てきましたが、スザンナの話はあべこべが起こらないというお話があって、そうだとするとフィレンツェのミステリヤの場合、啓蒙的な効果としては何が狙いだったのか、何を一番観客に教え込みたかったのかなということですね。三つ目は孔雀の羽が描かれているというお話がありましたが、本来聖人画に描かれる天使の羽は虹色になっているはずのところを、できないから孔雀だったり、安いとダチョウだったりということですよね。ダチョウとか孔雀の羽が描かれているのは、ジャンルとして聖人画と舞台画というふたつがあって、舞台は聖人画を真似し、画家は大人気だった舞台を絵にするみたいな、ある種のファンクラブ的な、メディアの往還があったのかなと思うのですが、そのあたりお伺いできれば。
杉山:台詞は、日本人が五七五を詠むとなんとなく節回しがついてしまうのと同じように、たぶんイタリア人であれば、オッターヴァ・リーマのようにちょっと唄うような感じになってしまうみたいです。ですので、朗唱していたというような言い方で問題ないかと思います。スザンナの話、農民・田舎者同士の裁判のエピソードがどういう啓蒙を生むかということですけれども、ひとつは弱い人や苦しんでいる場をみて上から笑うという品のないフィレンツェ市民の、そういうことですね。
楯岡:それは娯楽というような?
杉山:そうですね、娯楽になるわけです。それに加えて、結局賄賂で判事は買収されてしまうという話なんですよ。「ああ、こういうのあるある」というところで楽しむ見方もあったんだろうなと思います。直接はその二つなんですけど、実はそれはプロローグであって、その後スザンナの話になるんですが、スザンナがお風呂に入っているところに後ろから老人二人が出てきて「騒ぐとここでお前が間男をしたということを言うぞ」と、証言者は他にいないと、その二人はじつは判事でもあるのですが、「ここで黙って犯されていればお前は幸せになれる、けれどもここで声を上げて抵抗すれば、お前は間男を引き込んだということで死刑になる」と。どっちか選べということで、スザンナは神様はきちんと見てくださっているから死んでも構わないと大声を上げるんです。その後、裁判で彼女にはいったん死刑判決が下されるんですね、判事自身が偽証するわけです。その後ダニエルという聖人が現れて、二人の判事をそれぞれ別個に尋問して、証言に食い違いがあると、この二人は嘘をついているということで、逆にその判事二人が石を投げられて殺されるというそういうお話なんです。要するにプロローグと本編と一連の裁判の話になっていて、判事はとんでもない嘘つきばっかりだということが共通項になっているんですけども。プロローグで、救われないままに「信仰を捨てる」とまで言って舞台を去って行かなければいけない田舎者の姿は、今の感覚ですけどもかわいそうで仕方ないんですね。救われないままなんだというのがどうしてもあるので、これを聖史劇の特徴として入れたんですね。ただ、話としてつながっているのはつながっているんです。結局そういう悪い判事はきちんと懲らしめられなければいけないだから神様を大事にしようという啓蒙的なメッセージがあるにはあると思います。
最後、羽についてですが、お金がないときはダチョウの羽を使うんですけど、ダチョウの羽を七色に染めて使うんです。お金がないときは、きちんと教義に則った翼を作るんですけど、お金があるときはそのときで一番高価な羽といわれている孔雀の羽を使って「どう、うちの兄弟会こんなの手に入れたんだけど」、ということを隣の『キリストの昇天』を作っている兄弟会に見せつけると。絵画と演劇がお互いにお互いを参照しあって、どんどんどんどんリアリティを練り上げていくというのはおっしゃったとおりで、そういうところが面白いなと思っています。
楯岡:その舞台画というのは、宗教画に分類されるんですか?
杉山:舞台画というジャンルはないんですよ。宗教画の中に舞台的な表象が紛れ込んでいる。舞台そのもの、ワンシーンを絵にしましたということはなくて、断定できる作品もないのは事実です。それが面白くて、絵画のルールがある中で、画面にポンと、絵画のルールを逸脱するような翼を背負ってみたりだとか、頭に明らかに被り物をしているとか記号をはめ込むと。その記号の水準の誤差が鑑賞者にどういう効果を与えるのかなというところが面白いんです。例えば『キリストの昇天』という作品には「雲」という装置があって、そこにキリストが乗り込むという演出があったといいましたけど、今日は挙げませんでしたが、アンドレア・マンテーニャという画家の『キリストの昇天』という有名な絵があるんですんけど、キリストが雲に乗っていて、結構硬質な質感で描かれている雲なんですけど、その背景にも雲が描かれているんですね。その雲はふわっと消えていきそうな、いわゆる背景の雲、風景画で描かれていそうな雲。この2種類の雲、明らかに質感の違う雲が同じ画面に同居している効果、というのはすごく面白いと思うんですよ。リアリティの水準の違いがあって、鑑賞者に別の記憶をぱーんとフラッシュバックさせるような、そういう効果。いわゆる15世紀の宗教画を見ている人は、聖書の一場面を思い出しなさいということを教わっていたわけですけれども、そうは言いつつも絵の前で以前に見た宗教的なスペクタクルを思い出して、「ああ、あのときのマリアかわいかったなあ」などと思っていたかもしれない、それが私の考えていることなんです。
楯岡:鴻さんにお伺いしたいのですが、「イプセンは演出がないとできなくなった」とおっしゃっていましたが、現代においての多様な可能性という意味ではもちろん演出が必須ではありますが、その当時、イプセン作品の上演に際して演出がどうしても必要であったとは私はこれまで思っていなかったので、どういう観点なのか、お聞きしたいです。
鴻:これはですね、トルストイやドストエフスキー、つまり19世紀のリアリズム長編小説といわれているものが、19世紀社会というものをいろいろな形で非常に詳細に描いてきたわけですけれども、それをもし仮に演劇にしようとすると、ものすごい短いものにしなくてはいけないわけですね。『罪と罰』という演劇をつくるとするじゃないですか。大部分のところは劇でできないわけですよね。ほんのちょっとだけやるけれども、戯曲台本の中にはほとんど書かれていないわけです。だけど、『罪と罰』という膨大な長編小説の細部というものは作家の頭の中にはあるわけですよ。これをどういう風に構想するのか。ということをやるために必要とされたのが演出家なんです。だから19世紀の終り、1880年くらいに演出家が登場してくるわけです。
例えばイプセンを演出するときに、マルクスとエンゲルスを読まなくてはいけないんですよ。エンゲルスが『家族、国家、私有財産の起源』を書くに当たって、参照した社会学者がいるんですね。それはモルガンという人で、モルガンの『古代社会』というのは、1878年に書かれてそれを基にしてエンゲルスが彼の代表作のひとつを書くわけです。この二つをイプセンが読んで『ヘッダ・ガーブレル』を書くんですよ。これの中に出てくるレェーヴボルグのモデルはモルガンですよ。だからレェーヴボルグはヨーロッパ、つまりノルウェーでスイスで産業革命以前の家内職業というようなものがどのような形で崩壊していくのかということを研究して、そして業績を上げてノルウェーに帰ってくるんですね。それを前提にしているということを演出家が読めなければ、単に痴話げんかになってしまうんですよね。つまりいわゆるブルジョワ社会における男女関係とか、ブルジョワ社会における家族制度というものを構想するために、登場人物が社会学者なんですよ。そういうふうなことを読み込んでいく作業は、イプセンがそのまま演出できればいいんですけど、演出家はイプセンの書いたものをただやればいいっていう話じゃないんです。演出家はそれがどういう意味を持つのかということで、演出ならばモルガンを読まなきゃいけないんですよ、エンゲルスも。そのために演出家が必要なんですよ。スタニスラフスキーの膨大な演出ノートを読めばよくわかるように、テキストと同じ量の演出ノートがある、あるいはテキスト以上の量の演出ノートがあるわけですよ。これはスタニスラフスキーがもしかしたらチェーホフに直接聞いたのかもしれないですね。自分で調べて、分析もして、これを演出家がやるわけですよ。だからそういう意味で、初めは書けなかったわけです。19世紀の新たなヨーロッパ社会の登場とともに、戯曲が消えていくでしょ。これは非常に重要なことなんですよね。1820~30年頃から、重要な戯曲がぱたっとなくなるんだよね。そして近代戯曲が書き始められる間に50年、作家たちは長編小説を書いていたんですよ。長編小説で一回書いた結果、戯曲が書けるようになるわけですね。ただ、戯曲を書けるようになったのはいいんですけど、その戯曲の意味が簡単にはわからない。それを解説し、解釈し、舞台にのせる演出家が必要になってきたんです。だから非常にはっきりしているんですよ。演出家が登場してきたときって。これ、意外と知られていないけど。例えば、ソフォクレスが自分で伝説を素材にして『アンティゴネー』を書くとか。『アンティゴネー』はソフォクレスが書いて、ソフォクレスが演出している、だから別にいいんですよ、自分で書いたんだから。だから長いト書きなんか必要ないわけですよ。そういう意味で、1880年前後というのは世界演劇史で決定的に重要な時期なんです。これは一回日本演劇学会の近畿支部、永田さんが大阪大学でやっていたときに呼んでもらってこの話をして、だれか批判してくれないかなと思ったんだけど、みんな納得しちゃってね、これは問題だなと私は思いましたけど。
楯岡:もうひとついいですか。そこから展開させたいのですけれど、新しい社会に対してその問題をどう描くかということを、作家たちはかなりの時間をかけて取り組んでいくわけですけども、そういう意味では20世紀初頭、イプセン以降、ものすごい速さで変わっていきますよね。その決定打がロシア革命だと思うんですね。実際そこで突然急展開したわけではないけれども、みんなが新しい社会がくるんだって一瞬信じた時代があって、そのときにこの『ミステリヤ・ブッフ』が書かれたわけです。しかも「ミステリヤ」を「ブッフ」にするという仕掛けをしたわけですよね。そのときにマヤコフスキーは最後に事物のユートピアを到来させちゃう。結局答えを出しちゃっているみたいなんですけれど、あれはマジなんですかね? 鴻さんどう思われますか? ほんと? それでいいの?、って、今の私たちだと思ってしまうんですけど。マヤコフスキー的にはどうなんでしょうか。
鴻:これは二通りの考え方がありますよね。要するに1918年に一瞬信じたということですよね。だけど1930年に死んだと、自殺したのか殺されたのかわかりませんけど、それまでに『南京虫』と『風呂』というのを書いているわけです。そこで疑問に付されてますよ。だから初めから信じてなかったかもしれないが、一回は信じたのかもしれないですね。ある種の革命の光明の中で、結局第二版を書いたときには、国内戦が赤軍側の勝利に終わったという、革命の勝利の高揚感で書き直されている。そういう意味で言うと、1918年から21年にかけて、新しい社会というのを作ろうと、そういう風なことですよね。もうひとつ重要なのは、事物のユートピアということを言うときに、構成主義というのはある種の機械とかそういうものを非常に重視する、建設を重視する、非常に近代的な革命後の未来像みたいなものを考える人が多いけれどもそれは正しくないと言っている重要人物がいて、ドゥルーズ・ガタリが『カフカ論』とか『アンチ・オイディプス』の中で言っているわけですけれども、未来主義、キュビズムは始原主義・アルカイズムを呼び起こすといっているんですね。未来主義というものが先鋭化すればするほど、アルカイックなものが浮上してくると。例えば、タトリンの第三インターナショナルの記念塔を見よと、ドゥルーズ・ガタリが言ったところですよね。要するにあの建物は三層構造になっていて、四角形と三角形と丸だっけ、幾何学的に構築されているんだけれど、1階は太陽の公転にあわせて1年に1回1周すると。2階は地球と同じように1日に1回回転すると。あとは月が地球を回るように1月に1回、回転すると。これは宇宙的リズムだというわけです。すでに構築体というものが幾何学的であり、そしてバベルの塔のような全体の枠組みの中にそういうものが配置されていて、その姿は幾何学的抽象性というものと呼ばれているんですけど、しかし有機的リズムであると。それを有機的構成主義と呼ぶわけです。そういうようなアンヴィヴァレンツな感覚というのが実はあって、さっきの『ミステリヤ・ブッフ』なんか、どっちなのと。どっちかじゃないって話なんです。無機的と有機的が同居する、その同居する瞬間というのが未来主義というものが出現してくるときの姿なのであると。『カフカ論』の中で出てくる話なんですけど、『迷宮』をどう考えるかとか、『処刑機械』をどういう風に考えるのかという中で出てくるんですけども。もうひとつ、エルンスト・プロッホの『この時代の遺産』という1920年代に書かれたテキストの論文集がありますが、プロッホのモンタージュ理論というのは、エイゼンシュテインが1923年に書いた『アトラクションのモンタージュ』を参照にしたかどうかはわからないのですが。プロッホにはマンハイムでのすてきなエッセイがあります。マンハイムというのはライン川沿いにある、選帝候がつくった町ですけれどもそのマンハイムの王宮の裏をライン川が流れているんですね。そのライン川をはさんで向こう岸に20世紀の初めにルートヴィヒスハーフェンというライン川に作られた港町なんですけれども、そこに巨大なアニリン・ソーダの化学工場が建てられていて、これが既に1920年代にあったらしくてですね、ヨーロッパ最大級の化学工場でして、これが2つ同時に見えるんです。フランクフルトから列車に乗ってマンハイムに向かうと、最初にその巨大な化学コンビナートが見えてくるんですね。モクモクと煙を上げていてですね、私はそこを1日うろうろしたことがあったんですけれども、それとマンハイムの古い町並みですよね。それが無媒介的に接続していくという、これがモンタージュであると。これが世界の今の構造であると、プロッホがいっているんだけれども、この考え方は、エイゼンシュテインの『アトラクションのモンタージュ』と同じだし、しかも彼の師匠であるメイエルホリドがですね、自分の演劇をモンタージュとして提示し始めるようになるということと密接な関わりがあってですね。『ミステリヤ・ブッフ』における切断されたもの、異質なものの無媒介的な結合としての『ミステリヤ・ブッフ』という風に考えていくと、この当時の世界像そのものが演劇になっていて、マンハイムにおいては明らかに空間そのものが『ミステリヤ・ブッフ』的なんですね。じゃあロシア・ソビエトにおいてはという話もありますが、自動車の登場であるとかそういったようなことも含めた形で演劇というものが、世界との関係の中で組み立てられざるをえないと。そういうようなことも含め、マヤコフスキーの読解をしていく必要があるなと私は考えています。
森山:いまの鴻さんの『ミステリヤ・ブッフ』のお話は面白かったです。そして杉山さんの聖史劇のお話でしたが、歴史上の断面とおっしゃっていましたが、あれがどういうお祭りなのかというのをはじめて具体的にわかった。大の大人が天使を空中浮遊させるために一生懸命になっていたんだなということを思いますと、ああ、こういうお祭りだったんだなと。たまたまこのお話を聞きながら思ったのは、聖史劇というのが「見て・聞く聖書」でもあり同時にまた、それ以上の何かでもあるということ、そこが面白かった。
先日必要があって、ギリシャ喜劇のアリストパネスの『アカルナイの人々』というのを読み直していたんですね。これは完全に道化芝居もいいところで、今スパルタとアテネが戦争しているんだけど、ディカイオポリスという主人公が――これは、ほとんどシェイクスピアの有名な道化フォルスタッフみたいな人物なんですけど――、「俺は絶対戦争はいやだ」って言って、たったひとりで勝手に講和して酒池肉林にふけって、それを誰も止められないというお話でね。それを読んだときに、悲劇と喜劇って、どこかで紙一重の部分があると思いますが、その鍵を握っているのは「道化」という存在だということですね。そのなんとも猥雑で下ネタ満載で、テコでも自分の言っていることを通す、そういう傍若無人な態度が、転覆的な力を持っている、というのが面白いんですね。
そういった「喜劇の転覆性」みたいなことと、聖史劇のディテールが重なってみえた感じがしたんです。見れば見るほど、かなり具体的な、「何のためにそれやってんの?」と思わずツッコミたくなるような情熱が重なって見えて、こういう力がないと演劇というものは他者を動かせないのかもしれませんね。ですから、「ミステリヤ」と「ブッフ」の関係というのはやはりすっぱりとは切れないものなのだということを、今日聞きながら思いました。
杉山:アブラハムが『受胎告知』を観ているときに、滑車のメカニズムに夢中になってしまうんですね。途中から事細かにどういう仕組みで動いていてというのを書いていて、天使が空を飛ぶということを教義として受け入れるということと、目の前の機械仕掛けの精密さ、精巧さに感嘆するということが普通に両立しているところが面白いなと。
森山:でも一歩間違えればバラバラになると。何馬鹿なことやってんのとも思えてしまうわけですよね。
杉山:そうですね。マリアの美しさとは、女装した男の子のあどけない感じだったとか、そういうことも含めて、どっちに傾いてもおかしくない状態でバランスが取れている。バランスを取りつつも、あんなにいろいろな意味で過激な上演をしているところに、ダイナミズムがあるのかなという気がします。
鴻:最後にひとついいですか。聖史劇における滑稽なる者というか、下劣な者というのは、タルコフスキーの『アンドレイ・ルブリョフ』を思い出すといいと思いますね。ロシア最大の最も重要な聖像画家の名前ですけれども、彼がどのようにして聖像画家になったのかという伝記的な形で描かれた長編映画で、その中に「スコモローフ」という道化が出てくるんです。極めて宗教的匂いの強い映画なんですけれども、同時にロシアの異教の祭りと、道化が結構重要な場所に出てくるんです。キエフ・ペチェールスキー修道院の階段の壁面に書かれた、最も有名な絵なんじゃないかと思うんですけれども、これが道化なんですよね。跳梁する道化たち。なんで修道院のこんな重要な壁面の場所に道化が描かれているのか。宗教的な聖なる空間にいろいろな形で見え隠れする道化たちというのが、ロシア文化の伝統で非常に大きな意味を持っているというね。だから突然『ミステリヤ・ブッフ』が出てきたのではなく、ある種民衆に受け入れられるようなかたちでの同居がある。だから『ミステリヤ・ブッフ』って民衆が見てわかるわけがないと言っていた人たちが沢山いるんだけれども、同時に多くの労働者たちによって、ものすごくちゃんとした形でというか、熱狂的に受け入れられた。それがひとつのロシア文化の伝統とも関係があると、そういった見方もできると思いました。
三浦:ありがとうございました。自問としていくつか、印象に残ったことを、僕の脳みそを開示しておきます。今日は本当にありがとうございました。聖史劇のことは本当に不案内だったんですが、森山さんもおっしゃっていたように、ああこういう祭なんだなと。ちょうど京都でも祇園祭をやっていましたが、よく似たノリもあったんだなと。ひとつ重要なことは、ゲイ文化というか、そういったアンヴィヴァレンツな問題があったということ。つまりタブーですね。タブーがひとつ活力になっていたのだということ。それと、僕はギリシャ悲劇以前なんてぜんぜん考えたことなかったんだけど、鴻さんの最初の解説で、行進があって入城があって広場があってと。行進、立ち止まって何かあって、入場、王の練り歩き、またそこに広場があると。行列とか行進とかが演劇の起源なのだということ。
この間公演で北京に行ってきたんです。韓国は行ったことあったんだけど、北京は初めてで。北京にインディペンデントシアターがひとつあって、そこの監督とプロデューサーと話していて印象に残っているんだけど、こう言われたんだよね。いまや共産主義国家とか社会主義国家は北朝鮮を除いて他にないぞと。それが印象に残ったんだよね。誤解を恐れずに言うと、キューバももちろんだめだし、北朝鮮しかいないんだよということをちらっと言っていたと。今日鴻さんがおっしゃった、ベルリンの壁崩壊以降の共産主義、社会主義というもののレジュメがまだできていないし、それがおそらく当然マヤコフスキー、『ミステリヤ・ブッフ』をやるということと、当然つながっていくんだということ。覇権国家であるアメリカの、アメリカナイズされた資本主義とか民主主義とかの問題はあるんだけど、そこの部分でマヤコフスキーを考えることで、僕は眺めようとしていたんだけど。イプセンの話もそうだけど、文脈をどのように捉えているのか、それをどのように解釈し、提示するのかということが19世紀以降の演劇なんだとすれば、当然、地点の『ミステリヤ・ブッフ』というのはそういう扱いを受けていくだろうと。ところで今日の話の大半はキリスト教の問題、ロシア正教の問題ですね。僕としては、とにかくキリスト教のことは今日全部わかったとします。今日の講義で全部わかった、OK。スーズダリにも行ったことあるし。お土産も買ったし。キエフの話もなんとなくわかっている。僕らは遠いものだとは思わない、思っていないけど、でも、例えばドストエフスキーの『悪霊』やっても、太宰の『駈込み訴え』やっても客の反応が薄いったらありゃしない。コンテキストの問題なんですね。それと共産圏の話と、ソビエト演劇の繁栄と没落。1918年に一瞬信じた問題。これは表現したいなと思っています。以上、自問。
本日はありがとうございました。
<了>
←前頁へ