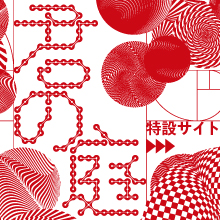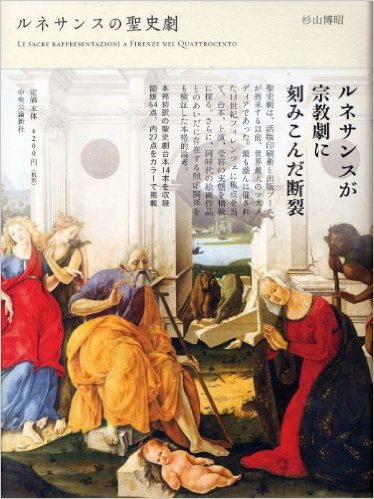6. 『聖体の奇蹟の聖史劇』より
ユダヤ人は騎士に:
聞いてくれ、騎士様、わたしの話をどうか、
わたしの死刑を延ばしてもらえないでしょうか。
わたしはこの悪しき世界から去るのです。
お願いです、すこしだけでも待ってもらえないでしょうか。
騎士は言う:
(藁で編んだ小屋に)入れ、こいつ、神の敵め、
悪しき仕業に及ぶとき、おまえは躊躇しなかっただろうが。
死刑執行人はユダヤ人に言う:
マヌエル、わかっただろう、この人はわたしを急かすのさ。
このなかに入れ、目方はメッゼッタくらいになるだろうよ。
ユダヤ人は焼かれる。
==
El Giudeo al Cavaliere:
Ascolta, cavaliere, el parlar mio
ed al mïo morire abbi avertenza.
Po’ ch’i’ mi parto di sto mondo rio,
priègoti ch’abbi un po’ di pazïenza.
El Cavaliere dice:
Entra costì, o nimico di Dio,
che al mal far non avesti avvertenza!
El Boia all’Ebreo:
Inteso hai, Manuël, come m’affretta.
Entra qua dentro, ché sarà mezzetta.
Arso el Giudeo.
==
La rappresentazione d’uno miracolo del corpo di Cristo, 1495, vv. 577-584.
テクストと絵画がたまたま一致しておりまして、ウッチェロの『聖餅の奇蹟』はこの聖体の奇跡の聖史劇を説明するときに引かれる図像資料なんですけども、ここでユダヤ人の親子が火あぶりになって処刑されています。
パオロ・ウッチェロ《聖餅の奇蹟》第5場面、1467-68年 国立マルケ美術館/ウルビーノ
これは伏線がありまして、同じような罪に問われたキリスト教の女性は救われるんですね。司法長官の夢にトマス・アクィナスが出てきて、この女性は救ってあげなさいという前振りがあって、その女性は救われるのですが、ユダヤ人はそのまま処刑されます。バフチンのいわゆる転倒を説明するに当たって中世の宗教劇というものは言及されることがあるんですけれども、イギリスの神秘劇なんかでいうとかなり該当する部分が多いのかなと、弱者が権力者をひっくり返すという構造は神秘劇や道徳劇、イギリスに関してはよく見かけますが、少なくともイタリアでは見られません。こういうところも、イタリアの聖史劇の評価がこれまで高まらなかった原因といわれます。つまり文学的に高く評価されなかったということなんですね。弱者がそのまま虐げられるだけのテクストなんて、読んでも仕方がないだろうと言われるわけです。ただではあっても聖史劇のテクストというのは研究するに値する価値があると思うのですが、それはこの私の本を買って読んでいただければいろいろ書いております。
『ルネサンスの聖史劇』杉山博昭(中央公論新社)
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AB%E3%83%8D%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%81%AE%E8%81%96%E5%8F%B2%E5%8A%87-%E6%9D%89%E5%B1%B1-%E5%8D%9A%E6%98%AD/dp/412004467X
次に演者の話をしたいと思います。女装する少年たち。教育的配慮と宗教的制限のもとに舞台に上がる少年。これはどういうことかといいますと、教育的配慮については先ほど言いました、ビジネスマナーを幼いころから叩き込むために、こういった人前でプレッシャーのかかる状況で言葉と身振りを実践する機会を少年に与えることが、フィレンツェの町をあげてのプロジェクトとして認められていたということ。一方、キリスト教は女性蔑視のように見られかねない点があって、当時、女性が舞台に上がるということはありえないことでした。そのため当時は、マリアもマグダラのマリアも聖歌隊の男の子がやっていました。なぜ聖歌隊かというと、高い声を出す訓練を積んでいるから、ということで聖歌隊の男の子を使ったわけです。ひとつ、
貴重な見物記録がありまして、「その大きくすばらしい椅子には若く美しい男性が座っている。彼は目を見張るほどの高価な若い女性の身なりをしていて、頭には冠をかぶり、その手に抱く書物を静かに読んでいる。このことすべてから推察するに、彼は最も清純な処女マリアを演じているのだ。」これはスーズダリの主教アブラハムという人が書いた手記(1439)なのですが、こういった記録が残っています。興味深いのは、彼はそこにマリアがいるとは書かないんですね。若く美しい男性がいるというところから記述を始めているところがとても興味深いところだと思います。このスーズダリというのはロシアでして、今日の裏テーマというのは、イタリアとロシアのコネクションということで、私は設定しておりますが、聖史劇研究において、アブラハムの手記がなければ、たぶん私はこの分厚さで本が書けませんでしたし、おそらくイタリアの聖史劇はほかの国の受難劇や神秘劇と比べて認められないままだったろうと、それくらい第一級の資料になっています。
そういう若い男の子がかわいらしい格好をしているとどういうことになるかというと、男色とか少年愛を喚起してしまうわけですね。当時のフィレンツェではこれがかなり社会問題として大きく認知されていまして、フィレンツェ政府が確か1440年代だったと思いますけど、男色や少年愛の行為を取り締まるだけの役所を立ち上げました。検挙者数は1000人とかそういう単位でいたんですね。そうした統計から見ても、ソドミーの慣習は宗教にとっても世俗の権力にとっても、忌むべき悪習だったことがわかるわけですが、そのキリスト教の中心的な行事である聖史劇にあってもこういった表象が行われているということは、非常に興味深い点だなあと考えております。当時の絵画を見ますと、確かに15世紀のイタリアの宗教絵画というのは、女性もそれほど女性的な身体的特徴を強調して描かれないことが多いんですね。これもその時点での図像制作の慣習がそうであったからこうなっているに過ぎないと言ってしまえばそれだけなんですけれども、当時の聖史劇の見物客がこの絵の前に立って鑑賞者になったときにどのような感情を抱くのか、ということは興味深いと個人的には考えています。
次に注目していただきたいのは、この二人の大天使ガブリエルとマリアです。
アレッソ・バルドヴィネッティ《受胎告知》第5場面、1447年 ウフィッツィ美術館/フィレンツェ
頭の上に光り輝く円盤がのっています。この円盤の下の面に頭の反射が映っているのがわかりますか?これが次のテーマなんですけれども。「贅を凝らした衣装」ということで、頭部に被る光輪、これが当時の聖史劇の創作団体である兄弟会の財産目録に「聖史劇用の光輪」ということではっきり記録が残っています。どういうものかというと、金泥で塗装された木製の円盤なんですね。他の図像資料を見るともっとはっきりします。デル・コッサの『受胎告知』です。
フランチェスコ・デル・コッサ《受胎告知》1467-69年 アルテ・マイスタ・ピナコテーク/ドレスデン
これはもう笑ってしまう感じなんですが、はっきりと被り物として描かれています。大天使ガブリエルが被っているもの、支持する部分も含めタケコプターみたいな感じになっているのがわかると思います。
加えてこのガブリエルの翼に注目していただきたいんですが、この翼、何を使っていると思いますか?
これも財産目録にのっているんですけれども、お金があるときは孔雀の羽を準備していました。お金がないときはダチョウの羽を買ってそれを染めて使っていたということが当時の会計帳簿から分かります。これも他にも作例はありまして、ここに孔雀の羽がはっきりうつってしまっていると。
ピエロ・デル・ポッライウォーロ《受胎告知》1470年頃 国立絵画館/ベルリン
こういった受胎告知は15世紀のフィレンツェを中心に描かれました。主要登場人物に関しては、絵画制作の規範に準じた衣装になっています。これは先ほどのアブラハムが言っているんですが、「まるで絵画から抜け出たようだ」という感想を残しているんですね。当時、兄弟会のスタッフが宗教絵画を見て、マリアはこういった服を着ているのだからこういう衣装を揃えましょうということで準備をしていたことは確かであろうと。しかし、それ以外の人物、宗教絵画に登場しないエキストラのような人物に関しては、同時代の15世紀のフィレンツェの服を着てそのまま出ていたことが確実ですね。要するにアナクロニズム、時代考証というのはまったく徹底されなかったということです。
補足ですが、わたしが現在進行形でやっている研究で面白かったのでひとつあげてみます。16世紀ローマのイエス役の衣装が大変面白くてですね、受難劇なので鞭で打たれたり、身体的迫害を受けるシーンが延々と続くのですが、そのシーンのためにイエス役がどういった衣装を着たかというと、生肉を貼り付けたボディースーツを着ていたらしいんですね。どこかで聞いた話です。そう、レディ・ガガそのままなんです。それを16世紀のローマでやっていたと。16世紀と21世紀の面白い一致があったので言いたくなったので言ってみました。
次に身振りの話ですね。聖職者の身振りに関しては、使徒・聖人・教皇、世俗の権力者の皇帝も含めていいかも知れませんが、おそらくこのあたりの役どころに関しては、聖職者の身振りを引用していただろうということは確かです。具体的にはどういうものかというと、ドミニコ会に残っているのですが、『聖ドミニコ9つの祈祷』ということで、祈りをささげる際に祈りの段階に従って、こういった身振りを取りましょうということが、修道会で決まっていたんです。
《聖ドミニコの9つの祈祷》14世紀 ヴァチカン図書館/ヴァチカン
それをそのまま状況に応じて演者に割り当てただろうということはおそらく確かです。こういった聖職者の身振りを使えない場合はどうするのかということですね。宿屋・居酒屋・大工、こういった登場人物がどういった身振りを使っていたかといいますと、これも当時の資料が残っています。居酒屋の主人はこういった格好をして、こういう身振りを取るよという書物が幸いにも残っていまして、これですね。
「居酒屋の主人」(ヤコブス・デ・ケッソリス『チェスの書』1493年)
手のひらを相手に向けているんですが、これは「ようこそおいでませ」というときに相手に感情を伝える、自分の掌を相手に向けるという身振りですね。このほかにも職業別の身振りが資料に残っています。では、ヘロデ・ユダ・悪魔という悪役に関してはどうかといったときに、これは大道芸人や吟遊詩人、マイム役者、道化の身振りを使っていただろうと言われています。つまり悪役に関しては恐ろしい身振りというよりも滑稽な身ぶりを取ったということですね。彼らは滑稽な道化だったと考えることができます。これは活人画の構図ですね。聖史劇がどういう風に上演されていたかということに関しては諸説ありまして、台詞や身振りはリアルタイムで付いているわけではなく、ただ単に活人画を上演していただけではないかという説もあるにはあります。そうだとすれば、その活人画の構図は宗教的な絵画の構造、立ち位置などは踏襲していただろうということですね。