かもめ
作品概要
2005年に野外劇場で、2007年にオペラハウスで上演した『かもめ』を装い新たにまったく異なるふたつの会場で上演。茶室版ではトレープレフは床の間に居座り、ART COMPLEX1928ではテーブルの上でタップした。このときの演出は後にカフェ・モンタージュ、アンダースローへと踏襲されていき、晴れて『かもめ』は地点のレパートリーとなることに。



撮影:阿部綾子
2011
日程・会場
2011.9.28-10.10 京都芸術センター 和室 「明倫」
2011.10.13-16 ART COMPLEX1928
原作
アントン・チェーホフ
翻訳
神西清
演出
三浦基
出演
安部聡子
石田大
窪田史恵
河野早紀
小林洋平
スタッフ
舞台監督:大鹿展明
美術:杉山至+鴉屋
特殊装置:石黒猛
音響:堂岡俊弘
照明:宮島靖和(RYU)
衣裳:堂本教子
テクニカル・コーディネーター:關秀哉(RYU)
宣伝美術:相模友士郎
制作:田嶋結菜
京都芸術センター制作支援事業
主催
合同会社地点
助成
芸術文化振興基金 EU・ジャパンフェスト日本委員会
製作
地点
共同製作
KYOTO EXPERIMENT
共催
KYOTO EXPERIMENT
劇評
観客にゆだねる表現の可能性
主人公の自殺で幕を閉じるのに、劇作家チェーホフは自作「かもめ」を喜劇と位置づけた。演劇の見え方は一面的ではないはずなのだ。京都に拠点を置く劇団「地点」の演出家三浦基は、新たな手法で「かもめ」を上演し、その多面性の実証を試みた。(13〜16日、京都・アートコンプレックス1928)
古典劇にありがちな、観客は見る側、役者は見られる側という固定した関係を解消するべく、舞台をせり出し、正面と左右の3方向に客席を置いた。開演前、俳優は客席にお茶を配りながら、小道具を説明し、登場人物の逸話を紹介する。今から始まるのは芝居だと虚構性を意識付け、観客が過度に感情移入せず冷静に見る空気を作った。
幕が開く。革命的な作家になりたいトレープレフ(小林洋平)、女優に憧れるニーナ(安部聡子)、息子トレープレフが書いた芝居を退廃的と揶揄する大女優アルカージナ(窪田史恵)、成功した小説家トリゴーリン(石田大)。筋は戯曲通りだが、せりふの言い方は様々。
普通にリアルな感情を込めたり、棒読みしたり、ミュージカルのように歌ったり。言葉の抑揚や速度、緊張感がめまぐるしく変容するうち、今見ている場面は悲しむべきなのか、笑うべきなのか。境界のあいまいな物語が立ち上がってくる。隣に座る客と自分の反応にずれが生じ始め、同じ芝居を見ながら別なものを見ていると実感させられる。
劇場で役者と空間を共有する観客が想像力を駆使し、目の前で繰り広げられている出来事を自分なりに咀嚼し、受け止める。その瞬間、初めて演劇は成立する。ネットやテレビにはない、完成を見る側にゆだねる表現にこそ、演劇の可能性があるという提起だ。
劇中、従来の文学に不満を抱くトレープレフが「新しい形式が必要なんです」と訴える。三浦はこのせりふを、一面的に物語をなぞる演劇に対するチェーホフの批判として舞台に昇華させた。
朝日新聞 2011.10.26
桝井政則
/blog/blog_comments/captcha
| 作品概要 | 2005年に野外劇場で、2007年にオペラハウスで上演した『かもめ』を装い新たにまったく異なるふたつの会場で上演。茶室版ではトレープレフは床の間に居座り、ART COMPLEX1928ではテーブルの上でタップした。このときの演出は後にカフェ・モンタージュ、アンダースローへと踏襲されていき、晴れて『かもめ』は地点のレパートリーとなることに。 |



撮影:阿部綾子
| 2011 | |
|---|---|
| 日程・会場 |
2011.9.28-10.10 京都芸術センター 和室 「明倫」
2011.10.13-16 ART COMPLEX1928 |
| 原作 | アントン・チェーホフ |
| 翻訳 | 神西清 |
| 演出 | 三浦基 |
| 出演 |
安部聡子 石田大 窪田史恵 河野早紀 小林洋平 |
| スタッフ |
舞台監督:大鹿展明 美術:杉山至+鴉屋 特殊装置:石黒猛 音響:堂岡俊弘 照明:宮島靖和(RYU) 衣裳:堂本教子 テクニカル・コーディネーター:關秀哉(RYU) 宣伝美術:相模友士郎 制作:田嶋結菜 |
| 京都芸術センター制作支援事業 | |
| 主催 | 合同会社地点 |
| 助成 | 芸術文化振興基金 EU・ジャパンフェスト日本委員会 |
| 製作 | 地点 |
| 共同製作 | KYOTO EXPERIMENT |
| 共催 | KYOTO EXPERIMENT |
| 劇評 |
観客にゆだねる表現の可能性 主人公の自殺で幕を閉じるのに、劇作家チェーホフは自作「かもめ」を喜劇と位置づけた。演劇の見え方は一面的ではないはずなのだ。京都に拠点を置く劇団「地点」の演出家三浦基は、新たな手法で「かもめ」を上演し、その多面性の実証を試みた。(13〜16日、京都・アートコンプレックス1928) 古典劇にありがちな、観客は見る側、役者は見られる側という固定した関係を解消するべく、舞台をせり出し、正面と左右の3方向に客席を置いた。開演前、俳優は客席にお茶を配りながら、小道具を説明し、登場人物の逸話を紹介する。今から始まるのは芝居だと虚構性を意識付け、観客が過度に感情移入せず冷静に見る空気を作った。 幕が開く。革命的な作家になりたいトレープレフ(小林洋平)、女優に憧れるニーナ(安部聡子)、息子トレープレフが書いた芝居を退廃的と揶揄する大女優アルカージナ(窪田史恵)、成功した小説家トリゴーリン(石田大)。筋は戯曲通りだが、せりふの言い方は様々。 普通にリアルな感情を込めたり、棒読みしたり、ミュージカルのように歌ったり。言葉の抑揚や速度、緊張感がめまぐるしく変容するうち、今見ている場面は悲しむべきなのか、笑うべきなのか。境界のあいまいな物語が立ち上がってくる。隣に座る客と自分の反応にずれが生じ始め、同じ芝居を見ながら別なものを見ていると実感させられる。 劇場で役者と空間を共有する観客が想像力を駆使し、目の前で繰り広げられている出来事を自分なりに咀嚼し、受け止める。その瞬間、初めて演劇は成立する。ネットやテレビにはない、完成を見る側にゆだねる表現にこそ、演劇の可能性があるという提起だ。 劇中、従来の文学に不満を抱くトレープレフが「新しい形式が必要なんです」と訴える。三浦はこのせりふを、一面的に物語をなぞる演劇に対するチェーホフの批判として舞台に昇華させた。 朝日新聞 2011.10.26 桝井政則 |
/blog/blog_comments/captcha





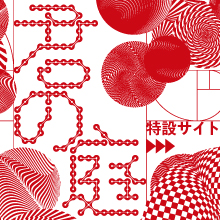



パリで研修していたとき、オペラ座でローラン・プティ演出の『若者と死』を観て、とても感動した思い出がある。音楽と振付によって、若者が首を吊るまでが叙情豊かに描かれる作品だが、その死の理由の本当のところがよく分からない。バレエ作品であるだけに、当然のことながら、無言のうちに話が進行するからだ。つまり言葉による説明がないわけだが、そこにむしろ妙な説得力があった。若者の死は、理由は実は何でもよくて、その死という結果だけが、無残にも必要とされるのだろう。
『かもめ』の最後で自殺するトレープレフという若者。今回の茶室版では、「トレープレフと自殺」というテーマがより明らかになったと思う。
昨今、無差別殺人に至る若者たちが一様に「誰でもよかった」とその動機を語る。刃物や銃口の向かう先が「誰でもよかった」のではなく、自分自身が「誰でもよかった」という、現代の憂い。さて、自分自身が誰でもよくなったトレープレフは、他人ではなく自分を殺すことを選んだ。自我の強い近代的な人間と言えばそれまでだが、自意識や自尊心といった自惚れから現代人が解放されている訳でもない。言葉を溢れさせることによって、チェーホフはそのことを描いたと感じる。しかし、では、言葉によって死の理由が明らかにされているかというと、そうでもない。トレープレフがなぜ死ぬのかは、やっぱりよく分からない。言葉の氾濫によって、チェーホフはこの不可解な「若者と死」を描いた。
2会場での公演が決まっていた今回、当初は共通のテキスト構成でやる予定だったが、茶室で稽古を始めて、徐々にトレープレフひとりの言葉に耳を傾けることになっていった。空間と言葉が影響し合うということを再確認するうれしい時間でもあった。ART COMPLEX 1928での公演では、全く別の『かもめ』が立ち現れることになる。よろしければ、そちらもご覧いただければ幸いです。
三浦 基
出典:当日パンフレット